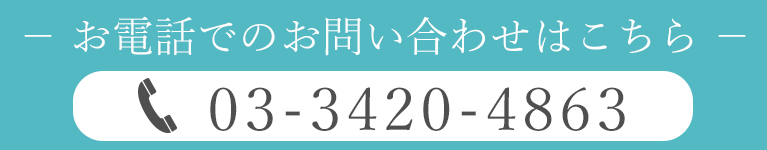糖尿病内分泌内科
糖尿病について
糖尿病とは、インスリン(血糖値を下げるホルモン)が不足したり、うまく働かなくなったりすることで、血糖値が高い状態が続く病気です。
この状態が続くと、 心筋梗塞・脳卒中・目や腎臓、神経の障害 など、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。
糖尿病の診断と現状
糖尿病は 血液検査で血糖値やHbA1c を測定することで診断されます。
日本では 約1,000万人 の方が糖尿病と強く疑われており、 予備軍を含めると2,000万人 もの人が高血糖の状態にあると言われています。
これは 決して珍しい病気ではなく、多くの方が向き合う必要がある病気 ということです。
ひとりひとりに合った治療を
近年、糖尿病の治療薬の選択肢が増え、年齢や体型、併存疾患などに応じた 個別に最適な治療 を選ぶことができるようになってきました。
「糖尿病はこう治す」という 決まった型ではなく、それぞれの生活や体の状態に合わせた治療が大切 なのです。
糖尿病に対する誤解をなくすために
糖尿病というと、「生活習慣病=自己責任」と考えられがちですが、 実は約半数の方は遺伝的な体質が関係しています。
このため、「糖尿病がある」というだけで偏見を持たれたり、本人が過度に責任を感じたりすることが社会的な問題になっています。
糖尿病は 正しく理解し、適切に付き合えば、安心して社会生活を送り、イキイキと過ごすことができる病気 です。
私たちは、糖尿病と向き合うすべての方が前向きに生活できるようサポートしていきます。
甲状腺機能異常症について
甲状腺(こうじょうせん)は、のどぼとけのすぐ下にある小さな臓器で、体のエネルギー代謝をコントロールする「甲状腺ホルモン」を作っています。このホルモンが多すぎたり少なすぎたりする状態を「甲状腺機能異常症」と呼びます。
主に以下の2つに分けられます:
- 甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう):甲状腺ホルモンが多くなりすぎた状態
- 甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう):甲状腺ホルモンが少なすぎる状態
これらは血液検査で甲状腺ホルモンの値や、特有の抗体を調べることで診断します。
甲状腺機能亢進症(こうじょうせんホルモンが多すぎる)
主な原因は「バセドウ病」という自己免疫の病気で、甲状腺機能亢進症の90%以上を占めます。特に20〜30代の女性に多くみられます。
主な症状
- 体重が減るのに食欲はある
- 暑がりになり汗が多くなる
- 動悸(どうき)や手のふるえ
- イライラ・落ち着かない
- 目が出てくる(眼球突出)
- 首の腫れ(甲状腺のはれ)
- 脈が速くなる
これらの症状があるときは、甲状腺の検査をおすすめします。
治療について
甲状腺ホルモンの値を正常に戻すことが治療の目標です。
まずは「チアマゾール」という飲み薬を使い、血液検査で様子を見ながら量を調整します。
※まれに、「無顆粒球症(むかりゅうきゅうしょう)」という副作用が起こることがあります。
38度以上の発熱や、のどの激しい痛みがある場合は、すぐに薬を中止して受診してください。
薬でコントロールが難しい場合や、重い症状(意識の低下、ひどい動悸、嘔吐、下痢、黄疸など)があるときは、手術やアイソトープ治療ができる専門病院をご紹介します。
甲状腺機能低下症(こうじょうせんホルモンが少なすぎる)
こちらは甲状腺ホルモンの分泌が不足している状態です。
多くの場合、「橋本病(はしもとびょう)」という病気が原因で、特に女性に多く見られます。
主な症状
- 疲れやすい・元気が出ない
- 寒がりになる
- 体重が増える
- 便秘
- 声がかすれる
- 肌が乾燥する
- 首のはれ(甲状腺のはれ)
このような症状があり、血液検査でホルモンや抗体の値を調べて診断します。
治療について
「レボチロキシン」という甲状腺ホルモンの飲み薬で、不足しているホルモンを補います。
治療を始めてから半年くらいは1〜3か月ごとに血液検査を行い、その後は半年〜1年ごとの定期検査で様子を見ます。
※中には治療が難しいケースや、脳からの指令に原因がある場合もあり、その際は専門の病院へご紹介します。
ヨウ素のとりすぎにご注意
昆布やイソジンうがい薬など、ヨウ素を多く含むものを日常的に使用していると、甲状腺機能に影響することがあります。心当たりがあれば、受診時にお伝えください。
甲状腺の病気は、きちんと治療すれば普段通りの生活を送ることができます。安心してご相談ください。