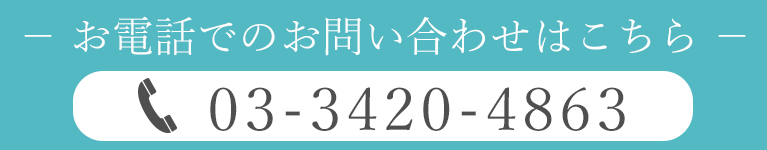生活習慣関連病ほか
脂質異常症は、多くの場合、健康診断や他の病気の検査で初めて指摘されることが多い病気です。
2019年の国民健康・栄養調査では、
- 男性:20歳以上で総コレステロールが240mg/dL以上の割合は 12.9%
- 女性:同条件の割合は 22.4%
この数値は年々増加傾向にあります。
脂質異常症が問題となる理由
コレステロールや中性脂肪が高くなると、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる ことが、国内外の研究で明らかになっています。
また、以下のようなリスク因子が重なると、より危険性が増します。
- 糖尿病
- 高血圧
- 肥満
- 喫煙歴
特に、すでに 心筋梗塞や脳梗塞を経験された方 は、より厳密なコレステロール管理が必要です。
脂質異常症の治療と予防
若くて特に持病がない場合、コレステロールを下げることによる健康効果は限定的とも言われています。
そのため、
- 年齢
- 性別
- 既往歴(糖尿病・高血圧など)
- 生活習慣(喫煙・食事・運動)
これらを総合的に評価し、本当に治療が必要かどうか を慎重に判断することが重要です。
過剰な治療を避けつつ、健康を守るためには、まずは生活習慣を見直しましょう。
生活習慣のポイント
- 食事の改善
・魚や野菜を中心とした 和食スタイル を取り入れる
・飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を控え、バランスの良い食事を意識する - 運動習慣の確立
・「ややきつい」と感じる 有酸素運動 を 1日30分 継続する
まずはご相談を
健康診断でコレステロールが高いと言われた方、脂質異常症が気になる方は、お気軽にご相談ください。
一緒に健康を守る方法を考えていきましょう。
肥満症とは?
肥満症とは、単に体重が多いだけではなく、肥満が原因で健康に悪影響を及ぼしている状態、または将来的に健康リスクが高まる状態を指します。
肥満の判断基準
肥満を理解するうえで重要な指標が「体格指数(BMI:Body Mass Index)」です。
BMIは以下の計算式で求められます。
BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)²
日本ではBMIが25以上を「肥満」と定義しています。
肥満の現状
2019年の国民健康・栄養調査によると、
- 男性:20歳以上の肥満の割合は 33% で、どの年齢層でも増加傾向
- 女性:肥満の割合は 22.3% で、特に若い世代では減少傾向
また、肥満の 90%以上 は、特定の病気や遺伝的要因ではなく、生活習慣など複数の要因が絡む「原発性肥満」とされています。
肥満が健康に及ぼす影響
肥満はさまざまな病気の原因となります。
- 生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症・慢性腎臓病(CKD)・痛風など)
- 動脈硬化関連疾患(心筋梗塞・脳梗塞など)
- 運動器疾患(変形性膝関節症など)
これらの病気は 生活の質(QOL)を低下 させ、寿命を縮めるリスクが高まります。
肥満症の治療
肥満症の治療では、健康状態を把握するための検査を行うだけでなく、心理的要因や社会的背景 も考慮しながら、医師と患者が協力して治療を進めることが大切です。
メタボリックシンドロームとの違い
「メタボリックシンドローム」は、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧・高血糖・脂質異常などが合わさった状態を指します。肥満と重なる部分も多いですが、必ずしも肥満である必要はありません。
健康的な生活を送るために、肥満のリスクを知り、適切な対策をとることが大切です。
骨粗鬆症とは?
骨粗鬆症とは、骨をつくる力と壊す力のバランスが崩れ、骨量が減って骨の強さ(骨強度)が低下する病気です。
骨がもろくなることで、軽い転倒やちょっとした動作でも骨折(脆弱性骨折)を起こしやすくなります。
骨折は生活の質(QOL)を下げ、寝たきりや生命予後にも関わる重大な問題です。
骨粗鬆症の現状
日本では、骨粗鬆症の患者さんは約1,200万人と推計され、その8割が女性です。
これは、女性ホルモン(エストロゲン)の減少が骨の代謝に影響し、特に閉経後に発症リスクが高まるためです。
また、超高齢社会の中で、男性を含む高齢者の骨粗鬆症も増加しています。
骨粗鬆症を疑うタイミング
骨粗鬆症は、加齢とともにその頻度が高まります。
特に以下のような方は注意が必要です。
- 50歳以上の男女(とくに閉経後の女性)
- 身長が若い頃より4cm以上縮んだ方
- 軽い転倒や動作で骨折をしたことがある方
- やせ型で体重が少ない方
70歳以上の女性では約4割に背骨の変形(椎体変形)があるとも言われており、定期的なチェックが大切です。
検査と診断
骨粗鬆症は、骨密度の低下や脆弱性骨折の有無により診断されます。当院では、DXA(デキサ)法というX線検査で骨密度を測定できます。骨密度は「YAM(若年成人平均値)」と比較して評価します。
以下の場合、骨粗鬆症と診断されます。
- 椎体や大腿骨近位部に脆弱性骨折がある
- 他の部位に骨折があり、YAMが80%未満
- 骨折がなくても、YAMが70%未満
骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症治療の基本は、「栄養」「運動」「薬物療法」の3本柱です。
栄養療法
骨の健康にはカルシウムとビタミンDが欠かせません。
その前提として、十分なエネルギーとタンパク質摂取により、サルコペニア(筋肉量の低下)やフレイルを予防することも重要です。ただし、腎機能に問題がある方は注意が必要ですので、腎臓専門医の診療をお勧めします。
運動療法
転倒予防のための体づくりが重要です。
日本整形外科学会が推進する「ロコモティブシンドローム(運動器不安定症)」対策としての【ロコトレ】(公式パンフレット)は、自宅でも取り組みやすく、効果的です。
薬物療法
骨粗鬆症治療薬は日々進化しており、カルシウム製剤やビタミン剤も含めると、多くの選択肢があります。
患者さんの年齢・生活状況・骨折歴・腎機能などを考慮し、一人ひとりに合った治療法を選択することが大切です。
当院での対応
骨と腎臓の関係は密接であり、腎臓専門医としての知見を活かした骨粗鬆症治療を提供しています。
気になる症状がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠中に「呼吸が止まる」または「弱くなる」ことで、睡眠の質が低下し、日中の眠気や集中力の低下など、日常生活に影響が出てしまう病気です。
診断の目安:AHI(無呼吸低呼吸指数)
睡眠1時間あたり、呼吸が10秒以上止まる“無呼吸”と、呼吸が弱くなる“低呼吸”の合計回数を指します。
oAHI ≧ 15:症状の有無に関わらず診断
oAHI ≧ 5:日中の眠気・いびき・高血圧・糖尿病などがある場合にも診断対象
原因と患者さんの傾向
- 閉塞型:呼吸の通り道(気道)が狭くなるタイプ。日本で一般的なのはこちら。
- 中枢型:脳の呼吸中枢の働きに異常があるタイプ。
主に50歳以上の男性に多く、女性でも10%、男性では10~20%程度の方が該当。思ったより身近な病気です。
こんな症状があればご相談を
ご自身で気づく症状:
- 日中の強い眠気・集中力の低下
- 起床時の頭痛や口の渇き
- 夜間のトイレ回数が多い
- 睡眠時間に比べて疲れが取れない
- 息苦しさで目が覚める
周囲の方が気づくサイン:
- 寝ている間のいびきや呼吸が止まっている
- 肥満、首まわりが太め、小さめのあご
特にご家族の指摘で気づくことが多いため、思い当たる場合はお気軽にご相談ください。
また、高血圧がなかなか改善しない場合、その背景に睡眠時無呼吸が隠れていることもあります。
放置せず、診断・治療をおすすめする理由
治療することで次のようなメリットが期待されます:
- 睡眠の質の改善と生活の質(QOL)の向上
- 心筋梗塞や脳卒中など心血管疾患のリスク軽減
- 居眠りによる交通事故や労働災害の予防
重症度が高いほど、健康リスクも高くなります。たとえば、**重症(AHI30以上)**の場合、死亡率が約2倍になるとの報告もあります。
検査と治療の流れ
まずはご自宅でできる簡易検査(OCST)を行います。
結果が
- AHI40以上 → そのままCPAP治療へ
- AHI40未満 → 精密検査(PSG:終夜睡眠ポリグラフ検査)をご案内します(専門機関にご紹介)
治療は、**CPAP(シーパップ:持続陽圧呼吸療法)**という機械を使い、睡眠中の無呼吸を防ぎます。当院では、呼吸の状態に応じて自動で空気圧を調整する「オートCPAP」を導入しています。
また、体重管理や飲酒・睡眠薬の調整も治療の一環となります。
当院での対応
当院ではPHILIPS社製の検査・治療機器を使用し、簡易検査からCPAP治療まで対応しています。また、専門的な精密検査(PSG)が必要な場合にも対応いたします。
「いびきが気になる」「日中の眠気がつらい」「高血圧がなかなか改善しない」といった方は、一度お気軽にご相談ください。
MASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)とは?
以前は「NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)」と呼ばれていた病気で、主にアルコールを飲まない方にみられる脂肪肝の一種です。肥満や糖尿病、あるいはその予備軍といえるメタボリックシンドロームなど、代謝の異常を背景に発症します。
ただし「アルコールを飲んでいないこと」が診断の前提だったため、現場での判断が難しいケースもありました。そこで新たに提唱されたのがMASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)という概念です。
簡単にいうと、「肝臓に脂肪がたまり、かつ代謝の異常がある状態」です。
この脂肪蓄積が長引くと肝臓に炎症が起き、さらに進むと「MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)」となり、肝硬変・肝不全・肝がんなどの重い病気の原因になります。
MASLDはどのくらい多い?
MASLDの有病率は世界全体で約25%。日本でも欧米と同様に高く、体格に関係なく見られます。
- BMI 23未満の方でも約10%
- BMI 30以上の高度肥満では80%
- 糖尿病患者では45〜60%とされています。
MASLDを疑うきっかけ
以下のような方では、血液検査などで肝機能の軽度異常(ASTやALTの上昇)が見られた場合、MASLDの可能性を考える必要があります。
- 肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常などの生活習慣病がある
- 健診で肝機能異常を指摘された
- エコーで脂肪肝と言われた
また、進行したMASH(隠れ肝炎)を疑うポイントとして、次のような所見があります:
- 手掌紅斑、くも状血管腫(皮膚の毛細血管が拡張)
- 血小板の減少(20万/μL以下)
- AST/ALTの比率の逆転(通常ALTが高め→進行するとASTが高くなる)
- FIB-4 index(血小板・AST・ALT・年齢から算出。1.3以上は肝線維化を疑います)
MASLDが進行するとどうなる?
MASLDの進行度、特に「肝線維化」の程度が将来の予後に大きく関係します。
実はMASLDの患者さんが亡くなる原因で最も多いのは、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患です。次いで多いのが、大腸がんや乳がんなどの他のがん。もちろん肝硬変や肝がんにもつながります。
そのため、消化器内科や循環器内科とも連携し、早い段階でMASHの可能性を見極めることが重要です。
検査と診断
MASLDが疑われるときには、以下のような検査を行います:
- 腹部エコー:肝臓が「白っぽく」映る高エコー像
- 腹部CT:肝臓の密度が低く見える所見
- 血液検査:ALT(GPT)が30U/Lを超える場合、炎症の可能性が高いとされます
※日本肝臓学会では「ALT>30」を早期診断の目安としています - FIB-4 indexなどで肝線維化の有無を確認します
MASLDの治療
MASLDの基本治療は、「生活習慣の見直し」です。
ポイントは次の3つです。
① 食事療法
- 適正なカロリーとバランスを心がけた食事
- 体重の5〜7%以上の減量が目標
- 最近注目されている時間制限食(夕食後から朝食まで12〜14時間食べない)も効果的です
※ただし筋力低下を防ぐため運動も重要です
② 運動療法
- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)
- 筋トレ(レジスタンス運動)
- 高強度インターバルトレーニングも有効とされています
③ 薬物療法
糖尿病を伴う場合、高インスリン血症を起こしにくい治療が重要です。
近年は以下のような薬で肝臓を守る効果も報告されています:
- SGLT2阻害薬(飲み薬)
- GLP-1受容体作動薬(注射薬)
それぞれに合った治療がありますので、ぜひ医師にご相談ください。
当院での対応
健診で「肝臓の値が高い」と言われた方、エコーで「脂肪肝」を指摘された方、あるいは健康診断の数値に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
早期発見・早期対応が、将来の重い病気を防ぎます。
高尿酸血症・痛風とは?
血液中の尿酸値が7.0mg/dLを超える状態を「高尿酸血症」といいます。この状態が続くと、尿酸が体の中で結晶化しやすくなります。関節に結晶がたまって炎症を起こすのが「痛風」、尿路にたまると「尿路結石」を引き起こします。
高尿酸血症・痛風はどのくらいいる?
高尿酸血症は、男性の約5人に1人、女性でも20人に1人にみられると言われています。痛風は特に30歳以降の男性に多く、日本全国で患者数が100万人を超えるとも言われています。生活習慣の変化により、年々増加傾向です。
痛風や高尿酸血症を疑うタイミング
- 家族に痛風の方がいる(遺伝的体質が関係します)
- **メタボリックシンドロームや慢性腎臓病(CKD)**がある
- 関節の激しい痛みや腫れ(特に足の親指の付け根)がある
→多くは1つの関節に急激な炎症が起き、発作のピークは24時間以内です
検査と診断
高尿酸血症の診断には、血液検査で尿酸値を測定します(基準値:7.0mg/dL以下)。さらに次のような項目も確認します:
- 腎機能、血糖、血圧、脂質(メタボとの関連)
- 尿中の尿酸量(尿酸のつくられすぎか、排出不足かを確認)
高尿酸血症の背景には、高血圧・糖尿病・肥満・心筋梗塞・脳卒中などが隠れている場合があり、慎重な経過観察が必要です。
高尿酸血症・痛風の治療
◉ すぐに治療が必要とは限りません
痛風発作がない場合は、すぐに薬を使わず生活改善だけで様子を見ることもあります。
◉ 治療のポイントは「生活習慣の見直し」と「薬」
▷ 生活指導
- 食事:プリン体・果糖・砂糖の取りすぎに注意
- 飲酒:ビール・日本酒などは尿酸値を上げやすいので節度を持って
○ 目安:ビール350〜500mL/日本酒1合程度/ウイスキー60mLまで - 運動:無酸素運動は控え、ウォーキングなどの有酸素運動を1日30分程度を目標に
▷ 薬物療法
尿酸を減らす薬には2種類あります:
- 尿酸を作るのを抑える薬
- 尿酸を尿から出しやすくする薬
※ 腎臓の状態によって使える薬が異なるため、心配な方は専門医にご相談ください。
! 注意点
尿酸値を急に下げすぎると痛風発作を誘発することがあります。そのため、発作中はまず痛み止め(NSAIDsやコルヒチン)で症状を落ち着かせ、発作後2週間ほどしてから尿酸値を下げる薬を開始します。
すでに治療中の方は、発作が起きても薬をやめないことが重要です。
当院での取り組み
当院では、腎臓専門医が高尿酸血症・痛風に対して、腎機能の評価を重視した診療を行っています。腎臓への負担を抑え、将来の腎不全を予防するためにも、適切な介入が重要です。
「尿酸が高いと言われた」「関節が腫れて痛む」「家族が痛風で心配」など、気になることがあればお気軽にご相談ください。